東大生と早稲田生のコスパ勉強法【化学編】
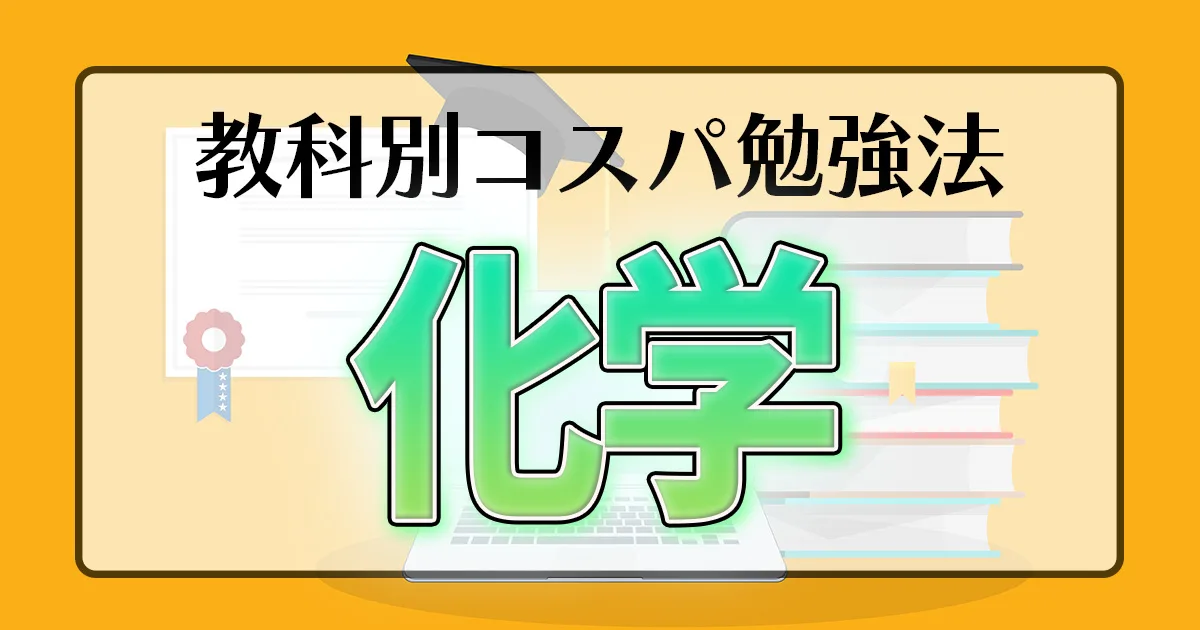
こちらのブログでは、勉強しない勉強法をスローガンに、最小限の努力で合格を目指すコスパ勉強法を紹介しています。
今回のテーマは「化学」です!物理のコスパ勉強はこちらから!
こんな人にオススメ!
- 覚えることが多くて頭がパンクしそう
- 勉強したことが活かせない、定着しない
このようなことで「化学」に苦手意識を持っている方は少なくないと思います。
そこで、今回はそのような方が必要最低限の努力で「化学」を克服できるような勉強法をお伝えしていきます!
この記事でわかること
- 受験科目「化学」の特徴
- 化学に必要な力と身につけ方
目次
はじめに
私たちが紹介するのはあくまで「コスパ」にこだわった勉強法です。
満点を目指さず、
合格に必要最低限な力を
必要最低限の努力で
身につける。
これが、私たちと読者の皆様の目標となっています!
※完璧な学力を身につけられるという訳ではないのでご注意ください。
化学という教科について
まず、コスパ勉強法をお伝えする上で、化学という科目の特徴を紐解いていきます。
化学の最大の特徴大きく2つ!
- 必要知識量が理系科目の中で多い
- 難しい問題が作りづらい
必要知識量が理系科目の中で多い
化学を勉強している方ならなんとなく感じているかと思います。化学は物理や数学と比べて、覚えることが多いです・・・
そのため、化学式や元素記号、炎色反応などいくら考えてもわからない知識問題も結構出題されます。
難しい問題が作りづらい
化学は必要知識量が多いがゆえに、そこまで問題が難しくならない傾向にあります。
物理や数学においての問題を解くプロセスと比較して説明します。
物理や数学
- 問題文読解力
- 思考力Lv.1
- 思考力Lv.2
この2科目は、問題を読解した後、思考力を問われる段階が複数に渡ります。いわゆる、閃きだったり、論理力だったりが高いレベルで求められます。
化学
- 問題文読解力
- 知識力
- 思考力Lv.1
一方、化学は先程も述べたように知識量がある程度必要です。この知識量を問うステップが1つ割り込んできます。そのため、数学や物理と比べて思考力を求めるステップが1つ少なくなるようなイメージです!
コスパ勉強法に必要な力
さて、ここまで化学を紐解いた上で最低限身につけるべき力をお伝えします。
それは、
「知識力」と「パターン化力」
です。順番に解説します!
コスパ勉強法①知識力
これはもう本当に単純な知識力です。
「知識量って単純な暗記でコスパとかあるの?」
そう思われる方もいらっしゃると思います。確かに、ある程度継続的な努力は必要になります。
しかし、ここで求めるコスパは、本当に必要な知識だけを、本当に必要な時間で身につける方法です!
必要な知識の身につけ方
まず、必要な知識を身につける方法としてオススメしたいもの。それは、高校でも基本配布される
資料集(化学版の辞書)を使う方法です!
この資料集、細かすぎると思う方が多いでしょう。しかし、実は非常にいいバランスで構成されています!
基礎の知識などはもちろん含まれています。さらに、かなり有用な発展知識もあります。ただ、数年に1度しか問われないような知識は載っていません。
資料集のバランスの知識量があれば、どの試験も合格ラインは確実に超えるでしょう。
※数年に1度レベルの難問は捨てます・・・
ただただ、資料集を暗記するだけでは途方もない作業になるので使い方までお伝えします!
資料集活用方法
- 1度、絵本感覚でさらっと読み切る
- 少しでもわからないところのページに付箋を貼る
- 付箋のあるページだけを1日20ページずつくらい読み直す
- 理解していれば付箋を剥がし、していなければ付箋はそのままにする
- 3と4を繰り返して、付箋がなくなるまで続ける
これで資料集から付箋がなくなればあなたも受験における化学の知識では敵なしです!
この資料集の活用方法にはいくつかメリットがあります。
資料集活用法のメリット
- 付箋を剥がしていく達成感が継続につながる
- 本当に必要な知識だけが無駄なく手に入る
- 広く浅く知識が身につき、それぞれを関連付けて網羅的に理解できる
3つ目のメリットは特に効果的です。なぜなら、忘れた知識でも他の知識との関連で思い出せるということが非常に多くなるからです!
化学の勉強を0からスタートしたい!という方は?
資料集の優秀さを解説しました。しかし、「化学の勉強をまだ始めたばかり!」という人には若干難易度が高いかもしれません。というのも、ボリュームは多いですし、解説もそこまで丁寧ではないからです。
そんな時には、市販のわかりやすいことを特徴とした参考書を使うことも1つの手です!
例えば、「橋爪のゼロから劇的にわかる」シリーズや、「宇宙一わかりやすい高校化学」シリーズがオススメです!この2冊は、どちらも図やイラストが非常に豊富です。化学が苦手もしくは、初心者の人でもスラスラ読めちゃう内容です。
知識の定着を0から始める方は、上記のような参考書も目を通してみましょう!
コスパ勉強法②パターン化力
冒頭でお伝えしたように化学の試験は難しくしづらいです。
つまり、基本問題またはそれをほんの少しだけ発展させた問題が9割です。
上の方法で身につけた知識量さえあれば、全部が例題レベルに見えてくるほどに難しいものはないと思ってもいいでしょう。
そこで、例題レベルで問題を解くためにも、どんな問題も例題のパターンに当てはめることが大事になってくるのです!これがパターン化力です。
問題が簡単ゆえの力ですね。
パターン化に慣れる
化学にはいくつかの公式がありますよね。
例)ボイル・シャルルの法則、質量保存の法則etc...
試験問題は問題文をこの公式に当てはめて解いていくのです。当てはめすればあとは計算したり代入したりするだけなので単純です。
この公式に当てはめる作業がパターン化です。
- 問題文を読む
- 図や式を利用して視覚的に理解する
- 当てはめる公式を探す
この3STEPはどの問題でも使えるはずです。学校での演習、自発的に解く問題集などすべてのタイミングでこれを意識しているだけで相当パターン化力がつきます!
パターン化力がつくと、一見難しいことを書いている問題でも、
「あー、またこのパターンね、計算するだけじゃん🎵」
というような余裕まで出てきます。笑
ぜひパターン化力を身に付けて学校の友達に楽チンそうな顔を見せてあげましょう笑
パターン化の練習にオススメできる易しめの問題集を以下で紹介しています!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
化学という科目が以前より簡単そうに見えてきたと思います。
まずは、何事も紐解いてみる。そして、必要な力だけを身につけることが最大のコスパ勉強法です!
物理のコスパ勉強法も紹介していますので、ぜひご覧ください!



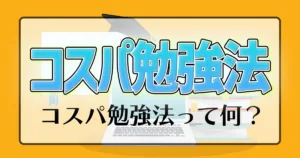
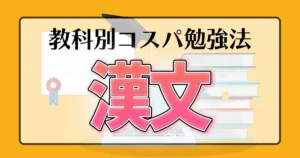
“東大生と早稲田生のコスパ勉強法【化学編】” に対して9件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。